
不妊治療の保険適用の改正、いったい何が変わったの?
2025/04/18
2025/04/20
不妊症は成人の約 17.5 % (世界の約 6 人に 1 人) が経験しており、日本でも5.5人に1人が不妊症ではないかと言われています。
大きな社会問題として認識され始めている不妊治療ですが、今までは一部の検査や治療は保険対象でしたが、体外受精などの高度生殖医療などは保険適応外とされており、高額のため実施が難しい人が多い状況でした。
しかし、2022年4月に保険適用が改正され体外受精などが保険適用の対象となりました。
不妊治療の保険適用の改正、いったい何が変わったの?
不妊治療は医療行為に該当しますが、今まではタイミング療法や排卵誘発、一部の検査以外には適用されない問題がありました。
体外受精などの卵管因子などの原因がある場合の有効な治療法が自由治療になっており、高額な金額でないと治療を受けることができませんでした。
一部の自治体では実際に体外受精などを受けた金額に支払われる特定不妊治療助成制度を利用していました。
また、不妊治療はタイミング療法のみが保険対象でしたが、助成制度では人工授精が対象にならない地域もあり、費用が一般不妊治療でも高額になる傾向がありました。
特定不妊治療助成制度とは
特定不妊治療助成制度とは、各自治体に居住する夫婦関係、もしくは事実婚関係にあるカップルが年齢制限や回数などの制限をクリアした場合に自費で実施した保険対象外の治療の一部を助成してもらえる制度です。
男性不妊の原因である精管閉塞、先天性の形態異常、逆行性射精、造精機能障害などに対する手術療法や薬物療法、女性不妊の原因である子宮奇形や感染症による卵管の癒着、子宮内膜症による癒着、ホルモンの異常による排卵障害や無月経などに対する手術療法や薬物療法などが対象となります。
初期は所得制限もあり、使い勝手があまりよくなく利用者が限られていたのが現状です。
2022年4月からの不妊治療の保険適応
しかし、2022年4月から不妊治療の保険適用範囲が拡大され、今まで保険対象外だった治療が保険適応になることで治療の負担が3割で診療を受けることが可能になりました。
不妊治療は長期にわたることが多く、費用も高額でした。
厚生労働省が委託して実施した調査研究の結果によると体外受精1周期あたりの平均費用は約50万円かかるとされており、何度も受けることが金銭的に難しい側面がありました。
そのため、今回の保険対象により今まで全額負担であった人工授精や体外受精を受ける方が増えることが予測されます。
高額療養費制度の対象
不妊治療が保険対象となることで高額療養費制度の対象となることが可能です。
高額療養費制度の対象となるのは健康保険が適用される診療に限定されているため、これまで人工授精や体外受精、男性不妊の手術などは同制度の対象外とされていました。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1ヶ月で上限額を超えた場合、超過した額を支給する制度となります。
「医療費」とは、病院等の医療機関にかかる診療費だけでなく、調剤薬局等で処方される薬剤費も対象に含むことが可能です。
年収や年齢により上限額が設定されており、それを超えた療養費を払い戻してくれます。
注意点として高額療養費制度は窓口で支払った後に払戻される制度なので、窓口で一時的に支払うことが負担となることがあります。
不妊治療の保険適用の注意点
2022年4月の不妊治療の保険適用改正で全ての治療や検査が対象となったわけではありません。
基本的には先進医療は健康保険の適用は受けられません。
しかし、保険診療と組み合わせて実施することで、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、健康保険の適用対象とすることが可能になりました。
この内容は全国健康保険協会では以下のように説明しています。
保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。この「評価療養」のひとつが先進医療なのです。
保険治療の適応の条件
不妊治療の保険適応は全ての人が受けられるわけではなく、条件が決まっています。
まず、年齢制限があり治療開始時において、女性の年齢が43歳未満であることが条件となっています。上記の図のように初めての治療の時点で40歳未満の女性は通算6回、40歳以上で43歳未満の女性は通算3回まで保険対象とすることが可能です。
|
の治療開始時点の女性の年齢 |
回数上限 |
|
40歳未満 |
通算6回まで(1子ごと) |
|
40歳以上43歳未満 |
通算3回まで(1子ごと) |
保険適用前に胚を凍結保存していた場合に、その胚を使用することで治療を受けると保険対象になります。(ただし、医療機関ごとに差異があるため要確認)
2022年4月前に助成制度を利用していた方は今後、助成制度は保険対象になったため当該助成制度は廃止になりますが、保険診療の回数制限に助成金の支給回数は反映されません。
特定不妊治療助成制度を利用して助成金を受け取った方でも、要件に該当すれば通算6回ないし3回まで、保険診療として不妊治療を受けることが可能です。
対象となる不妊治療
人工授精
人工授精とは、排卵日周辺に合わせて洗浄濃縮した精子をカテーテルと呼ばれる細い管を用いて子宮に注入する不妊治療です。
カテーテルを膣から子宮へ差し込み、中を精子が移動することで子宮までの精子の脱落を抑えることが可能です。
自然妊娠の場合、精液が入るのは子宮の手前となる腟の部分ですが、人工授精では精子を子宮の奥へ注入することで、受精の確率を上げることができます。
人工という名前ですが、精子を子宮に直接注入したあとの妊娠までの流れは、自然妊娠と同じため自然妊娠に近い不妊治療と言われています。
体外授精
通常、女性の体内で行う受精の過程を女性の体外で行う事で妊娠率を大きく上げる不妊治療です。
排卵誘発剤を用いて卵子を複数発育させ、良質な卵子を選別して使用します。
選んだ卵子を培養液が入っている容器に取り出し、精子を振りかけ受精させます。
受精した受精卵をインキュベーターで培養し、胚になった後に女性に胚移植を行い、着床を待ちます。
顕微授精
顕微授精は精子をガラスの鍼に入れ、卵子に直接注入する不妊治療です。
顕微授精は良質な精子を選び直接卵子に注入するため理論上では1つの精子に対して卵子が1つで受精が可能になります。また、直接注入するため受精する確率が大きい不妊治療です。
他の不妊治療では対応が難しかった男性不妊の無精子症にも精子が精巣に1つでもあれば対応が可能です。
まとめ
今回の不妊治療の保険適用は経済的負担という不妊治療を受ける上での大きな問題に対応した形になります。
これまでにも助成金などの制度はありましたが、地域により格差があったり所得や助成回数の制限により、活用が難しい場合が存在していました。
しかし、今回の保険適用により負担が3割にす抑えられるため、経済的な負担が大きく軽減され不妊治療を受ける人が増えると予測されます。
特に不妊治療は年齢と共に妊娠する確率が下がるため、これまでは経済面から治療を受けられなかった収入の少ない若い人が治療を開始するきっかけになり、不妊治療の成功率が向上していくことや、治療期間が短く妊娠できる方が増えていくことが望まれます。
不妊治療の費用負担軽減により今まで第2子出産に前向きに検討できなかった方でも検討が可能になるなどの影響もありそうです。
不妊治療を考えている人は保険適用をうまく活用し検討していきましょう。
-
PR
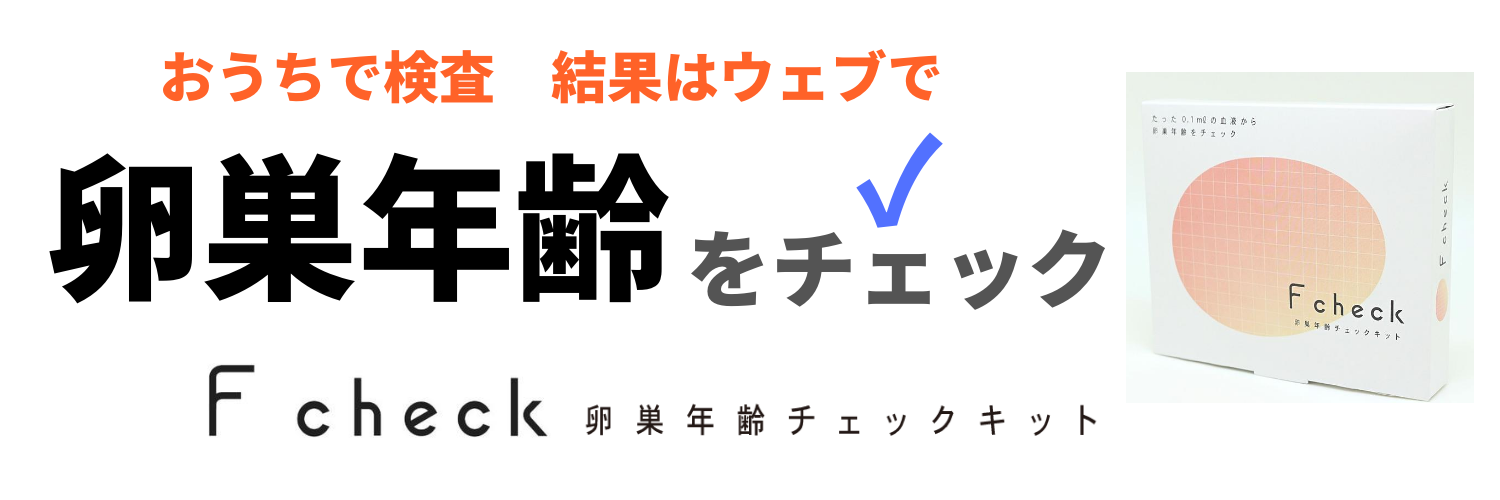
卵巣年齢を自宅で簡単にセルフチェックできる、日本初の検査キット【F check】とは?
-
おすすめの記事

治療費をローンで借りるって普通のこと?
- #費用
2018.04.25
2023.02.02
-
おすすめの記事

腹腔鏡手術経験者ブログまとめ
- #ブログ
- #手術
2016.02.04


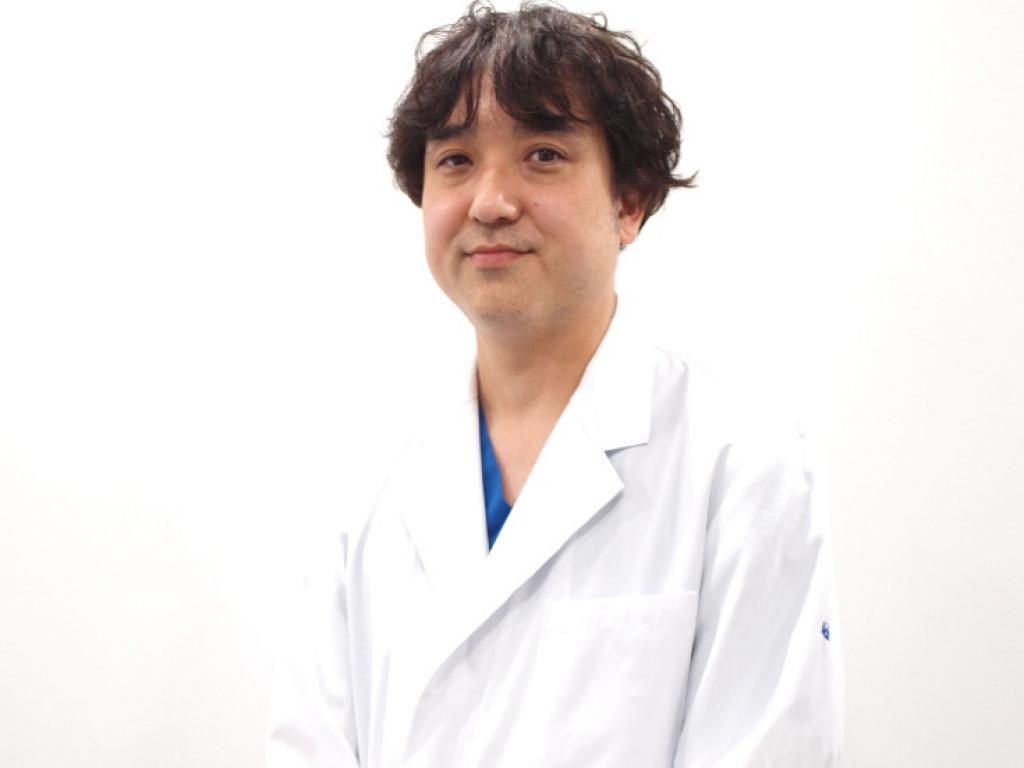
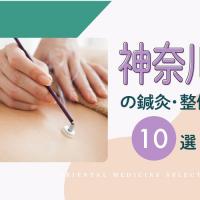



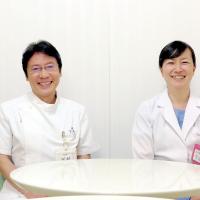
 }}
}} }}
}} }}
}} }}
}}










